
NOWEARMAN × 田中宗一郎

田中「うん。僕も出来れば、ずっと洋楽、邦楽っていう言葉は使わないでいたかったんですよ。昔から好きじゃなくて。〈スヌーザー〉をやっていた90年代後半から2000年代前半くらいまでは、わりと誰も洋楽とか邦楽っていう言葉を使わなくなった、っていう実感があったんです。ようやくそこが分け隔てなくなった。これはたまたまマンチェスターから出てきた音楽、これはたまたま福岡から出てきた音楽、これはたまたまベルリンから出てきたバンド、みたいになってきたな、これは楽しいな、と思ってたんですけど。でも、気がつくと、7?8年前から、洋楽、邦ロックっていう言い方がまたムクムクと出てきて。これは何が起こってるんだろう? っていう感じがしてたんです。だから、今もたぶん、NOWEARMANをやってると、『洋楽っぽいですね』とか言われるんじゃないですか?」
高藤「ああー、めっちゃ言われる」
田中「でしょ? それってちょっとむず痒いでしょ?」
長野「まあ、よくわからないというか。『洋楽っぽいのに何で日本語でやってるんですか?』みたいな質問とかは、いまひとつピンと来ないんですけど。別にそれは普通に、日本語でやるのが自然だから日本語でやります、っていうだけの話なんで」
田中「その質問をした人には若干失礼ですが、その質問はやっぱりおかしいから」
全員「(笑)」
田中「『洋楽っぽい』って何? って思うもん」
長野「そうなんですよね」
田中「だって、ファレル・ウィリアムスもアニマル・コレクティヴも、全部"洋楽"じゃないですか? それをひとまとめにするのかよ! っていう。分析的になると、それだけ邦楽っていうのが、あまりに音楽的に狭められている、っていうことだと思うんですけど。J-POP的じゃないものは全部洋楽、っていうふうになる。これ、楽しくない話だから、このへんで止めときましょうか?」
全員「ハハハッ!」
田中「じゃあ、NOWEARMANの話を。初めて観させてもらった時に、ア・サーテン・レイシオなりジョイ・ディヴィジョンなりイギリスのバンドと、ニューヨークのバンドが浮かんだところがあったんですけど。その時に思ったのが、温度で言うとホットというよりコールド。ジャンルで言うと、すごく乱暴だけど、ア・サーテン・レイシオが出てきた時にホワイト・ファンクって言われたみたいに、やっぱりこれはファンクの一種である、と思ったんです。そのコールドっていう部分は、まあ冷たいとも言えるし、冷めているとも言える。ファンクっていう部分は、要するにねじれのあるビートみたいなものですよね。で、そういうふうに、NOWEARMANがタグ付けされた時にどう感じますか?」
長野「あまり熱くなり過ぎないような音楽の作り方というか、それこそクラウト・ロックとか、デトロイト・テクノみたいな、美学があった上でそこにディティールとしての情熱、熱さを乗せる意識で作っているので、温度感がすごく熱くはない、って言われることに関しては、まったくその通りだと思います。ファンクに関しては......音楽性云々ではなく、自分たちが音を出す上で面白いというか、美学とは別の部分での音楽に求めるものがあると思うので、その部分がビートのねじれ感に繋がっているんだと思うんですけど。どちらも言われて嫌な気はしないですね」

高藤「たぶん、コールド・ファンクって、うちらを聴いて言ってくれたのがタナソウさんだけだと思うんです。僕はそれがすごい嬉しかったんですよね。NOWEARMANは、熱いものを敢えて殻みたいなもので隠して、クールに見せているところがあって。で、僕自身も自分の中にはドラマーとしてのファンキーな部分がすごくあるんですよ。細かい16ビートとかが実は全部隠されてる8ビート、みたいなものを意識して演奏しているんです。そこを見抜いてもらったのが、すごく嬉しかったですね。本当の黒人にはかなわないけど、そういうのを大好きでやってるのをここに出して演奏している、っていうのをわかってもらえたって。普段はあんまり言われないけど(笑)」
長野「言われないね(笑)」
田中「わりとよく言われるのって、どういうこと? いい部分も含めて」
長野「それこそ、『洋楽っぽい』(笑)」
高藤「あ?、言われるねえ」
長野「形容しがたいんですかね? あんまり知らない、って感じで」
高藤「で、結局、シンプルとかタイトとか、そういうことになるけど。実は内側にあるカオスなものっていうか、すごい細かいものっていうのは、なかなか」
田中「でも実際、今回のタイコの金物とかの録り方って、すごく意識的ですよね? スネアとかキックのちょっとリヴァーブ音が少なめで、アタック音がクリアになる鳴り方とか。ベースのアタック感ある感じの録り方も。ああいう録りって日本のレコードにはないな、っていう感想は持ちました。今回みたいな音作りって結構大変なんですか?」
高藤「いや、基本的はいつもライヴでもそうなんですけど。必ずミュートはして、倍音なく、っていうのは意識してやってる感じです。ハイハットも敢えて強弱をそんなにつけないで、あんまりバウンスしないように叩くとか。ただ、レコーディングではそれをよりいい感じにしてもらっていて」
BACK / NEXT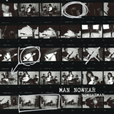
NOWEARMAN
「MAN NOWEAR」
←INTERVIEW TOP
←MAGAZINE TOP
[MENU]
┣NEWS
┣DISC
┣ARTIST
┣MAGAZINE
┣MAILING LIST
┣CONTACT
┗HOME
Copyright(C) Spectrum Management Co.,Ltd. All rights reserved.