
NOWEARMAN × 田中宗一郎

60年代のヴェルヴェット・アンダーグラウンドに始まり、テレヴィジョン、スーサイド、コントーションズ、ソニック・ユース、そしてラプチャーやストロークスまでが名を連ねるニューヨークのバンドの系譜。あるいは、ア・サーテン・レイシオやジョイ・ディヴィジョンを擁するマンチェスターの〈ファクトリー・レコーズ〉。海を隔てたその二つの音楽都市/シーンが撒いた種を、まさに今、ここ日本で芽吹かせようとしているのが、長野智、高藤新吾、中村大樹からなるスリー・ピース、NOWEARMANだ。
アジアン・カンフー・ジェネレーションの後藤正文のプロデュースによってレコーディングされた1stアルバム『MAN NOWEAR』に詰まっているのは、歪なファンクネスやアヴァンギャルドなアート志向を体現した先人たちの遺伝子。別の言葉に置き換えれば、00年代以降のインディを通過した感性で生み落されたコールド・ファンクやポスト・パンクといったところだろうか。しかも、この三人は、それをJ-ROCK的な世界観が支配的な島国において、如何にポップへと展開出来るかというトライアルにも挑もうとしている。この大きな野心を内に秘めた作品のリリースに際し、メンバーの三人と、元〈スヌーザー〉編集長/現〈ザ・サイン・マガジン・ドットコム〉クリエイティヴ・ディレクターである田中宗一郎で対談をおこなった。
(文/構成:小林祥晴〔ザ・サイン・マガジン・ドットコム〕)
田中宗一郎(以下、田中)「最初にライヴを観させてもらったのって、いつ頃でしたっけ?」
長野智(以下、長野)「一昨年の秋くらいですかね? あの時は、ライヴの後、〈スヌーザー〉の話を俺が一方的にして(笑)。なんか、『生〈スヌーザー〉だ!』って」
田中「そうか(笑)。それは俺がしゃべってることが〈スヌーザー〉っぽかったっていうこと?」
長野「そうです、そうです」
田中「(笑)確かあの時、こっちは感想を言ったんだよね? ドラムとベースのリフでリズムを組み立てて、それが曲のベースになってて、みたいな話で」
高藤新吾(以下、高藤)「そうですね。曲に対する瞬間的な分析がすごくて。一回聴いて、あんなに言われたのは初めてだったんで」

長野「しかも、すごいピンポイントで、狙いが合ってて。その時に初めてお会いしてお話したんですけど、『やっぱり、すごいわ』って(笑)。なので、今日はすごい光栄なんですが、緊張してます」
田中「ゆっくりやりましょう。じゃあ、まず、遡って訊かせてください。中村さんと長野君は10年近い付き合い?」
中村大樹(以下、中村)「そうですね」
田中「当初から、わりとリズム・ベース、リフ・ベースで曲を作っていくんだ、っていうのはあったんですか?」
長野「最初はそういう感じじゃなくて。もともと中学校が同じだったんですけど、音楽を聴いていく中で、たとえばドアーズを知ったらドアーズみたいなのをやったりとか、いろんなものを一緒にやりながら、だんだんバンドを形作っていったんで。コンセプトが最初からあって、こういうのをやりたい、っていうのじゃなかったんですけど。でも、前のドラマーが辞めて新吾さんが入ってからは、ジョイ・ディヴィジョンとか、最初からバンドでやりたいことが明確にあったんで、少しずつそれに詰めていったっていう感じです」
田中「どうでしょう? 今、ジョイ・ディヴィジョンっていう名前が出ましたけど、ロール・モデルにしていたバンドは幾つかあるんですか? 今のNOWEARMANを聴かせてもらうと、まず二つ、なんとなく思い浮かぶんですけど。ひとつは、ヴェルヴェッツから始まって00年代のブルックリンへと至る、いろんなタイプのニューヨークのバンド。で、もうひとつは、UKの〈ファクトリー〉周りのリズム・ベースのバンドっていう」
長野「やっぱり一番最初にヴェルヴェット・アンダーグラウンドがあって、それに影響を受けたバンドにも影響を受けていたんで。ジョイ・ディヴィジョンとか、スーサイドとか。ストゥージズもそうなんですけど。70年代、80年代くらいのニューヨークのアンダーグラウンドのバンドから、ノーウェイヴのコントーションズとかDNAとかまで、リズム主体でアヴァンギャルドで、っていうのに自分たちのサウンドを寄せていきたかったんです」
高藤「そうだね」
長野「ただ、ニューヨークは新しいものを生み出す力やアイデアはすごいと思うんですけど、メロディは圧倒的にイギリスのバンドの方が優れていると思っていて。で、ノイ! とかのクラウト・ロックや、初期のカン、DAFもすごい好きなんですけど、ディティールに関してはそういうドイツのバンドの方が優れていて、緻密にきちんと作り込んでいる。で、日本に関しては、それを解体して、ちゃんと解析して、もう一回組み立てることが出来る、って俺は思ってるんですね。だから、今、日本で自分たちがやるにあたって、日本はいろんな国のものをクロスオーヴァーさせて組み立てることが出来るんだ、と信じてやっているというか」
田中「日本の場合、いろんなものを解析して、それをコンバイン出来るんだ、っていう確信を持っているのは、自分たちが今そう出来ると思っているからなのか。それとも、日本にはいろんなものを分析して掻き集めて違うものにする歴史みたいなものがあって、その一部に自分たちがいる、っていう感覚なのか。どちらの方が近いですか?」
長野「日本でそういったことをやっているバンドのモデルが、具体的にあるわけじゃないんですけど。たとえば、ジャックスとか(裸の)ラリーズあたりの日本のバンドは、一番最初の出発点はヴェルヴェット・アンダーグラウンドで。それこそ、ニューヨークのノーウェイヴのバンドとスタンスとか、最初に持っているものは同じだと思うんですね。でも、それがだんだん違ったものになっていったっていう。それっていうのは、やっぱり日本ってアイドル文化がすごいからだと思うんですよね。ピンク・レディーだったり80年代のアイドルって、〈モータウン〉とかディスコとかファンクとか、いろんな海外の音楽を解体して、わかりやすくして組み立て直した結果として、ああいうふうになっていると個人的には思っているんです。なので、そういった歴史の基盤の上に、今のバンドがいる状態だと感じていて。なので、バンドがそこをまた解体して、さらにもう一度、組み立て直してみたら面白いんじゃないか、と思ってます」
田中「そのへんの、日本人がやる時の身振り、手癖みたいなものを意識するようになったのはいつ頃ですか? 僕らの世代だと、わりと屈託なく海外のものに影響を受けてやるっていう感じだったですけど、NOWEARMANはもう少し俯瞰的で客観的な見方じゃないですか」
長野「でも、もともと、音楽を邦楽と洋楽って分けて聴いて来なかったんで。だから、そういうふうにメディアで扱われていることに、『あっ、そうなんだ』って」
田中「逆にビックリするっていう」

長野「そうですね。そういう感覚でみんなは物を作ったり、聴いたりしているのかな、と後から意識するようになって。というか、最初は日本の音楽をそんなには知らなかったんで。それこそ、中学校の頃に流行ってたのはスピッツとかミスター・チルドレンとかで、テレビやラジオでいっぱいかかってるのを自然に聴いている、っていう感じで。それと一緒に、U2とかレディオヘッドとかオアシスとかも聴いてたんで、そんなに日本のバンドみたいにどうとか、海外のバンドみたいにこうとか、っていうわけではなく。国がどうこうっていう意識はなかったんですけど」
→NEXT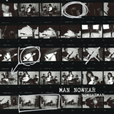
NOWEARMAN
「MAN NOWEAR」
←INTERVIEW TOP
←MAGAZINE TOP
[MENU]
┣NEWS
┣DISC
┣ARTIST
┣MAGAZINE
┣MAILING LIST
┣CONTACT
┗HOME
Copyright(C) Spectrum Management Co.,Ltd. All rights reserved.