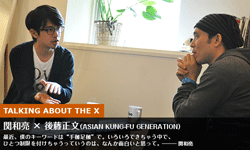
──関さんは、Perfumeをはじめ、たくさんのアーティストの方々のミュージック・ビデオを作られていますよね。
関「おかげさまで、たくさんやらせていただいていますね」
後藤「同じ人が撮った、たくさんの作品を観るのが初めてだったので、作品を見比べてしまったんですけど。でもあれですよね、広告代理店的が入ったっていうかクライアント仕事っていうのもありますよね?(笑) 作品を見ていて、気を使っているなって感じるところがありました(笑)。サカナクションとかだと、アーティストと密にやっている感じがするし、Perfumeも信頼関係が表れているし。いろんな仕事のやり方があって、面白かったです」

関「真面目な作品とかありましたよね(笑)。 結構、映像作家って紹介されることがあるんですけど、自分では作家性とか気にしていないというか。アーティストというよりは職人っぽい感じなのかなって、自分では思ってるんです」
後藤「作品ごとに違うとは思うんですけど、特に主眼っていうか主題というか、どういうところに自分の気持ちをフォーカスしているのかなって訊いてみたいと思って」
関「こういう曲でこういうアーティストさんなんですけど何をやってくれますか?って言われた時に、これをやります!って一行とか二行で言えるようなことを大事にしていて。例えば、サカナクションだったら、『文字を出してそれが見えるところどころで違う』ってことがやりたくて。ボーカルをカッコよく撮ってくれとか、女の子をきれいに撮ってくれとか、オーダーがあればやりますけど、自分的には重きを置いてなくて。これはやりたくないっていうのも逆にないですけどね」
──そういう中で、自分の流儀としてこれだけは譲れない部分って何かありますか?
関「自分がその曲を聴いた時に、この音が鳴っているからこういう絵を入れたいっていうのは、すごくあるんですよ、音楽ビデオだし。それが、そうじゃないんじゃない?って言われると、いやいやいやいやっていうのはりますね。そこは、譲れないので説き伏せるというか、話し合いますね」
──関さんは、現在の会社に'98年に入社されて、この世界に入って12年以上とのことですが、映像の世界に入ろうと思ったきっかけは何だったんですか?
関「きっかけは、中高生と単純に音楽が好きだったってことですね。田舎は長野県で、すごくローカルな所なんで、CDを買いに行くのに時間がかかる場所だったんです。だから、音楽に触れるには自分から積極的に求めないと入ってこなくて。で、いろいろCDを聴いたり、ミュージック・ビデオもどんどん見るようになって。後藤さんは同世代だからわかると思うんですけど、テレビでやっていた『BEAT UK』をずっと観てました。それを観て、音楽って音だけではなくて映像で伝えるっていう世界があるんだと刺激を受けて、こういう仕事をやりたいと思ったんです」
──結構、早い段階で将来の夢が固まっていたんですね。
関「そうですね。高校生のときには映像の世界に入ることを決めていました」
後藤「高校卒業後は、どちらに進学されたんですか?」
関「僕、東京の大学に一瞬入学したんですけど3ヵ月くらいで辞めてしまって、その後はバイトをしていて。たまたまそのバイト先の店長と映画監督の方が知り合いで、それがきっかけで映像の現場、Vシネマとかドラマとかを紹介してもらって、バタバタと下積みを重ねてました。19歳とか20歳くらいのときですね」
後藤「現場に飛び込んでいったんですね。叩き上げですね」
関「そうです。完全に叩き上げです。映像の学校にも行きましたけど、そこで覚えたことっていうよりは、現場で覚えていったことの方が大きいです」
後藤「そういうのって、この対談を若い子が読んだとして、意外と現場でやったことの方が大きいんだなって参考になりますね。現場の経験の方が役立っているって、実感されているってことですもんね?」
関「僕は、学校で習ったこととかって、そんなに役に立たなかったから。現場に3ヵ月とか半年とか入れば、言葉で覚えることができますしね」
後藤「僕は静岡県出身ですけど、昔って田舎には、いろんな孤島みたいなのがたくさんあって、情報鎖国みたいなね(笑)。でも今は、インターネットがあるっていうのはものすごく大きくて、能動的に動けば何でも知ることができるから、今の時代を生きている若い子をうらやましく思うけど。まぁ、その情報が本当か嘘かは、いよいよ分からなくなってきた部分もあるけどね。かといって能動的に何かをやっているかっていったら、そうでもないと思うし。例えば、私も映像作品を作ってみたい、PVを撮ってみたいって思ったら、型を押したようにそういう学校に通ってしまうと思うんですよね。その型への押されかたって、僕らが学生の頃から窮屈だなって感じていたけど、それにしてもなって思うところはありますよ。何にも変わらない」

関「映像系とか美術系の学校に、PV学科っていうのがあるんですよ! それを聞いたとき本当にビックリして! “バカヤロウ! PV学科って何だそれは!?"って(笑)」
後藤「いいですね(笑)。そういう話が聞きたいです」
関「(笑)。PV学科は本当にビックリして、“PVとはこう作るんです"って、多分やってるわけですよね。嘘〜!?って思いましたよ」
後藤「最初に囲ってしまうとね」
関「そうなんですよ。今、後藤さんの話を聞いて本当にそうだなって思って。僕、面白くないなって思うのは、PVってPVっぽいのがいいとされる風習があって。さっき、後藤さんがクライアント仕事がっておっしゃっていたのは、PV然としているってことなんだろうなって思ったんですけど」
後藤「そうそう。 アーティストが出てきて、演奏をよく撮って顔をフォーカスしたりしてね。サカナクションの『アルクアラウンド』が面白いのは、一郎君とか全然ピンボケで、分かってんだか分かってないんだかのところを歩いていたりとか。他のメンバーもチラッと出てくるだけだし。そういう、カメラワークの面白さがあるんですよね。でも作品全体で通すと心に入ってくるものがあるっていうか。ハッとするところもたくさんあるし。でも、他の人のことは言えないけど、メンバーの顔ばかりが映っているPVもあって。果たして、そういうPVは、曲の宣伝になっているかはわからないなと思うこともあって。その人たちの顔を覚えてもらうにはいいかもしれないけど。それって、音楽をメインとしているっていうよりは偶像を売ってる気がするんですよね。だから、そういうのは観て歴然としてるなって。でもそれが、Perfumeだったら彼女たちそのものをアイドルとして面白く撮るってことだと思うから、マッチしていると思うし。でも、この人たちをよく撮ったところでなっていうのもあると思って、自分たちのPVにも言えることかもしれないけど。僕たちをよく撮ったところで何が広がるんだろうって思うこともあります。自分が好きな海外のバンドの人たちのミュージック・ビデオとか見てても、そこにはフォーカスされてないものが多いんですよね。個人的には、本人たちが出てこないものが好きではあるんです。ただ、さっきも言ったOK GOのミュージック・ビデオとか、これ何回やったんだろうなっていう。その手間とか面白いなって思うんですよね。日本のPVって、必要以上に広告化し過ぎているっていうか」
NEXT / BACK
→関和亮(セキカズアキ)-PROFILE-
←INTERVIEW TOP
←MAGAZINE TOP
[MENU]
┣NEWS
┣DISC
┣ARTIST
┣MAGAZINE
┣MAILING LIST
┣CONTACT
┗HOME
Copyright(C) Spectrum Management Co.,Ltd. All rights reserved.