
クリス・ウォラ インタビュー
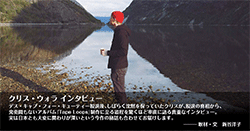
結成時から17年にわたりギタリスト兼プロデューサーとして、ヴォーカルのベン・ギバートと共にデス・キャブ・フォー・キューティーを牽引してきたクリス・ウォラが、バンドを脱退したのは昨年9月のこと。以来その動向に注目が集まっていたが、ここにきて自ら主宰するレーベルTrans Recordsから送り出した2枚目のソロ・アルバム『Tape Loops』はなんと、アナログ・テープに録音した音源を切り貼りして作ったループで構築した、インストゥルメンタルのミニマルなアンビエント・ミュージック。ブライアン・イーノの1970年代のアルバムを想起させ、デス・キャブ〜の諸作品とも、7年前に発表したソロ1作目『Field Manual』とも全く異なる音楽性を提示している。そんな驚くべきサウンドで新たなスタートを切ったクリスに、バンド脱退の理由や『Tape Loops』誕生の経緯を訊いてみると、デス・キャブ〜に言及する際には言葉を何度も選び直したり、じっと考え込むこともしばしば。他方、『Tape Loops』の話となると、俄然口調も軽くなる。いまだ過去と未来の狭間にいる、彼の葛藤をリアルに感じさせる語り口が、誠実な人柄を浮き彫りにしていた。
(取材・文:新谷 洋子)
最近ノルウェイの北極圏にある町に引っ越したそうですね。あちらに家族がいるんですか?「実は僕の家族は4代前にノルウェイから移民してきて、20世紀の初めからシアトルに住んでいるんだ。だから僕のルーツはノルウェイにある。遠い親戚もいるよ。でも今回引っ越したのは、それとは関係なくて、妻がノルウェイの大学で学ぶことになったのさ。今は事実上、北極に住んでいることになるね」
慣れるまで大変だったのでは?「そうでもないよ。どこかアメリカの北西部に似たところがあって、親しみが湧くんだ。ほんと、シアトルに似ていて、しかもノルウェイ北部の人たちはみんなフレンドリーだし、みんな英語を話すし、不思議なくらい苦労はしなかったよ(笑)」
偶然にも新しい土地で、アーティストとして新しい出発を切ることになって、意識の転換が容易になったようなところはあるのでしょうか?「う〜ん、今はノルウェイとアメリカの間を往復しながら生活していて、それが現時点での僕の状況を物語っているような気がするんだ。というのも、僕はまだ音楽的な意味で片足を過去に置いている。一生懸命前進しようとしていて、バンドとは別個の、独立したアイデンティティを確立しようと試みているわけなんだけど、それは途方もなく大きなチャレンジなんだよ。なんたって一組のロックバンドの一員として、17年間を生きてきた。つまり、大人になってからの全人生だろう? そこから自分を切り離して、アイデンティティを刷新するとなると、長い時間を要する。僕がデス・キャブ・フォー・キューティーのメンバーとしての最後のライヴ(注:2014年9月13日)をプレイしてから、すでに1年以上が経った今でも、まださほど距離を感じないし、生活パターンも完全に切り替わってはいない。デス・キャブ〜の一員というアイデンティティは、いまだ強い磁力を発しているんだよね。そんなわけで、確かにノルウェイでの生活に助けられたところはある。でもシアトルにしょっちゅう戻ってくるから、なかなか難しいものだよ」
そもそもは、これまでデス・キャブ〜の全作品のプロデューサーも務めてきたあなたが、今年春にお目見えした最新作『金継ぎ(Kintsugi)』にいたって「これはプロデュースしたくない」と感じたのが、脱退に至るひとつの前兆になったそうですね。「うん。それから実際にバンド脱退を決めて、ほかのメンバーに告げるまでに、半年くらいの時間を経ているんだ。具体的には、僕がプロデュースを辞退して、最終的にリッチ・コスティを起用してレコーディングを始めてから約1カ月経った時点で、脱退を決心した。プロデュースしないという決断が、直接脱退につながったわけじゃないんだ。あれはすごく自然なリアクションで、僕がやらないほうがうまく行くだろうという、言わば実用的な判断だった。でもその後作業を続ける中で……僕の心が100%そこにないように感じてしまった。バンド結成以来初めて、自分は何か別のことをやっているべきなんじゃないかと思い始めたのさ。それが何なのか分からなくて、今もまだ明確には見えていないんだけど、とにかくバンドから離れるべき時が来たと気付いたんだよ」
脱退の意思を公表した時には、「未知の世界に惹かれる」とも話していました。バンドに意外性や新鮮味を見出せなくなったという面もあったんでしょうか?「僕が思うに……ある程度予測がつくようになったにも関わらず、それで楽になるんじゃなくて、逆に音楽作りを続けることが困難になったーー意味不明かもしれないけど、そういうことなんだよ。バンド活動について僕が厄介に感じていたことは、どれも、本来はちっとも難しくないはずのことだった。なのに何もかも、折り合いをつけるのが不可能なように思えた。パーソナルな意味で、乗り越えられない気がした。自分が知り尽くしていて、確立されていて、すっかり馴染んでいるものを放棄するというのは、簡単なことじゃない。僕はこのバンドに山ほどの時間と思い入れを注ぎこんできたし、もちろんリスペクトと愛情もたっぷりある。でもそれらは必然的に、クリエイティヴな対立やパーソナルな対立を伴うもので、そういう葛藤をひとつひとつ解決するプロセスにおいて、もはやほかのメンバーと一致点を見出せなくて、前に進めなくなってしまったのさ。もちろんバンドに留まることもできたよ……恐らく永遠にね。でも僕はハッピーじゃなかったんだ」
脱退を決めた頃には『Tape Loops』に着手していたんですか?「うん。『金継ぎ』をプロデュースしたくないとほかのメンバーに告げた瞬間に、着手したと言えるんじゃないかな。つまり脱退前から取り掛かっていたんだ。あの日はさすが、みんな大きなショックを受けていたけど、僕の想いを理解してくれた。実際、アルバム制作は行き詰まっていたからね。だから一旦みんなスタジオから引き揚げたんだけど、まだまだスタジオは使えたし、僕自身も早速、“さてと、じゃあどうしようか?"という大きな疑問と向き合わなくちゃいけなかった。それか次第に、“僕はいったい何者なんだろう?"という問いへと変わっていった。“今の僕にとっていい音って何だろう? デス・キャブ〜のアルバムをプロデュースすることに満足できないなら、僕を満たしてくれるのは何だろう? 僕は何を選択するんだろう?"と。『Tape Loops』はそういった疑問に対するひとつの回答なんだと思う。ほら、僕が音楽的に、自分の中から自然に湧き出るものを表現できる環境に置かれた結果が、このアルバムなんだ(笑)」
じゃあアナログ・テープを加工してループを作るという作業は、これまでもずっと好きでやっていたことなんですね。「ああ、長年やってきた。元を正せば、14〜15歳の頃にアンビエント・ミュージックの類を聴き始めてのめり込んだのが、全ての始まりかな。ブライアン・イーノは僕にとって最大のヒーローのひとりだしね。その上、最近の僕は、ミニマリズムの進化形を探るミュージシャンたちをたくさん発見して、聴き漁っていたんだ。それぞれに異なる形でミニマリズムを掘り下げていて、そういったアルバムと非常に密な関係を築き上げていた。彼らの音楽が、僕の友達になってくれたんだ」
いくつか例を挙げてもらえますか?「もちろん!例えばティム・ヘッカー(Tim Hecker)はモントリオール出身のミュージシャンで、ノイズ寄りのサウンドスケープを作る。時として不安感をかき立てて、ヴァイオレントで感覚を逆なでするようなところさえある音楽なんだけど、それを実に美しく仕上げるんだ。あとは、fennesz+sakamotoだね。数年前にNHKワールドで坂本龍一に関するドキュメンタリー番組を見て、言うまでもなくYMOの音楽は知っていたし、彼のサウンドトラック作品も幾つか聴いたことがあったんだけど、番組の中でクリスチャン・フェネスとのコラボレーションに触れていて、俄然興味を惹かれた。以来、この名義でリリースされた2枚のアルバム(注:2007年の『cendre』と2011年の『flumina』)は、過去10年間の僕の最愛のアルバムと化したんだよ。ここにきて、ミニマリズムは新たな豊穣の時を迎えているんじゃないかな。本当に美しい作品が続々誕生しているし、今年はマックス・リヒターの新作『Sleep』も素晴らしかったね」
→NEXT
←INTERVIEW TOP
←MAGAZINE TOP
[MENU]
┣NEWS
┣DISC
┣ARTIST
┣MAGAZINE
┣MAILING LIST
┣CONTACT
┗HOME
Copyright(C) Spectrum Management Co.,Ltd. All rights reserved.