
NOWEARMAN × 田中宗一郎

田中「そこを考えると、何だろうな? 若干あるのは、岡村ちゃんは、ヴァースとコーラスのメロディ・ラインの譜割で、極端に刻み方が変わるんですよ。で、これはもう、敢えて言います。長野くんのヴォーカリスト、メロディ・メイカーとしての弱点は、譜割が一拍目から入ること。そして、ひとつひとつの刻みがちょっと長めであること。岡村ちゃんの場合、刻みがすごく細かいんですよ。ラップまで行かないけど、細かいし、シンコペーションするし。だからこそ、コーラスに来た時の長めの旋律が生きる。だから、もし違いがあるとすれば、そこかも」
長野「なるほど。ヴォキャブラリー的なものですかね、曲に対しての」

田中「で、なおかつ、長野くんの声ってすごく通るバリトンだから、良くも悪くも、声自体の存在感が強いんですよ。だから、"Stars"のコーラスみたいな、一番高いところが出る時に、なおかつ震えてるみたいなのは、すごい気持ちいいんだけど。逆に、ヴァースとかで押さえて歌ってる時の、なおかつ声が太くて、ちょっと揺れてるみたいなのは、ある意味、古風でダークに映るかもしれない。すごく失礼なことを言ってると思うけど。で、極端な話、世の中の音楽を聴いてる人の8割は歌しか聴かない。その人たちは別に能力が低いわけじゃなくて、それに慣れてるからなんですよ。その人たちは潜在的に音楽を欲しているわけだから、NOWEARMANが本当に広く、っていうのであれば、トラックの部分に関しては何も変える必要はない。ただ、メロディ・ラインと長野くんの声の聴かせ方? もしかしたら、ヴァース部分ではもう少しか細くていいのかもしれない。デヴィッド・シルヴィアンが呟くようにヴァースで歌っている、っていうのでいいのかもしれない。そういうちょっとしたアイデアが、広げるっていう意味では一番デカいのかも」
高藤「目から鱗だね、本当に」
長野「勉強になります」
田中「アメリカのヒット曲は、今スカスカなんですよ。EDMは音を埋めまくってるんだけど、いわゆるベース・ミュージックとかからの影響を受けてるものって、バック・トラックがスカスカで。あれとか知ってる? ジェシー・Jとアリアナ・グランデとニッキー・ミナージュの女子アイコン三人がトリプル・ヴォーカルで歌ってる"バング・バング"とか? 六週間とか八週間くらい全米のトップ10の中にいる曲なんだけど、これとか、よく出来てる。この曲は、ベース・リフってスリー・ノートなの。ドンッ、ダラダラ、ドンッ、ダラダラ、って一曲それだけ。変化なし。でも、上モノとヴォーカルのメロディ・ラインで4分半くらい聴かせてしまう。ニッキーはラップをやるんですよ。で、アリアナとジェシー・Jの二人はヴァースではすごい伸ばす。コーラスでは、バンバン、ダラララ?、っていう刻みで聴かせる。だから、もしかしたら、そういう今のアメリカのポップスにメロディ・ラインのヒントはあるのかも」
長野「なるほど」
田中「今アメリカのポップスは面白いよ。それ自体で100点はつけられないんだけど、『これをレフトフィールドなサウンドの中に落とし込むには?』っていう発想で引っ張れるアイデアがすごくある。EDMじゃないほうの、ちょっとR&B寄りだったり、トラップ以降のヒップホップ的なものとかは、ダーティ・プロジェクターズなら聴いてる、っていう感じだと思うし。レフトフィールドの連中のアイデアをメインストリームの連中がパクッていくし、今度はメインストリームの奴らがやっていることに対抗してアンダーグラウンドのバンドがやる。そういう意味では、アメリカのインディ・バンドはメインストリームと繋がってるんですよね。すごい健康的なの」
高藤「ああー」
田中「だから、どっちも楽しい。日本だとそこがバッサリとオール・ジャンルで分断されているから。要するに、AKB48が取り入れるアイデアなんて皆無なわけだから。しかも、日本の場合、インディ・シーンはインディ・シーンで、メインストリームのJ-ROCKシーンはJ-ROCKシーンで、それぞれでやってる方も、特にお客さんは満足しているっていう。俯瞰して見るとね。だから、そこをクロスオーヴァーさせたいと思っている人も、実はそんなに多くなくって。後藤(正文)くんはそうじゃない? クロスオーヴァーした方が面白いって。僕も明らかにそうなんですよ。でも、後藤くんがやるとアーティスト発信だから、まだ納得されるところがあるけど、僕が間に入って、メインストリームと今のアンダーグラウンドをクロスオーヴァーさせようとすると、結構嫌がられるっていう(笑)。『あっ、これ難しいな、お客さんが嫌がるんだ』っていうのは、感じたことあります」
長野「でも、だからこそ、もっと面白く耕すっていうことをこれからやっていく必要があるっていうか。うちらみたいな無名のバンドを後藤さんがプロデュースしてくれるっていうのもそうだと思うんですけど。自分自身が音楽から受けてきた愛情を返して、また新しく、面白くシーンを盛り上げていきたい。そういうことだな、とはすごく思うので」
高藤「そうだね」
長野「あと思うのは、バンドと〈スヌーザー〉というメディアが、一緒にもっと上手い関係性を築けてたら、受ける側の印象も違ってただろうなって。だから、レディ・ガガのやつ(*〈スヌーザー〉2010年6月号の「特集:レディ・ガガに勝てない日本のロック」
のこと)を読んだ時に、すっごい面白いと思ったんですよ。日本でそういうことを言う人たち、いなかったし。サッカーのワールドカップの時に、『メディアは自分たちのチームに、もっと厳しくしなきゃいけない』みたいなことが今さら言われたりしましたけど、俺からしたら、『いや、そんなこと、〈スヌーザー〉はもっと前にやってたよ』って」
田中「ハハハッ!」

長野「でも今は、まだ2000年代のメディア、バンド、〈スヌーザー〉が耕した土壌でやってる印象で、まだ新しくは耕せてないな、とは思うんで。だから、タナソウさんに、『もう一回〈スヌーザー〉やってください』ってみんな言うんですけど(笑)、そうじゃなくて、あの人が命をかけて作った土壌を自分たちがちゃんと引き継いで、あの人が見た時に、『ああ、面白いじゃん』っていう感覚のシーンにしていかなきゃいけないっていう......謎の使命感があります(笑)」
田中「でも、辞めて3年経って、そのせいで生き生きと大きくなったところもあるし、〈スヌーザー〉みたいなメディアがなくても頑張ろう、形にしよう、っていう意識を持ってくれてるバンドが、パイとしては大きくなってないけど、明らかに数として増えた。で、その両方が起こったことには、苦々しい気持ちとエキサイトしている気持ちの両方があるので。絶対に楽しくなるはず。本当に今は、いろんないいバンドが5年前と較べれば数がいるし、それのサウンドは全部バラバラだし。で、明らかに今メインストリームで売れてる、5万人のフェスに出る、ミュージック・ステーションに出るバンドよりも、絶対に面白いと思っているから。それは本当に、下駄を履かせて言っているわけじゃなくて、海外のインディ・バンドを聴いているのと同じ気分で聴けるのが100はいると思っているので。だから、来年、再来年ですよ。それは〈サインマグ〉も必死に頑張るし、100のバンドがそれだけやってくれれば、近い将来にはいろんなことがゴロッとひっくり返るはず。なんか、また話が逸れちゃったけど(笑)」
全員「(笑)」
BACK / NEXT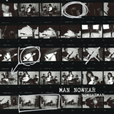
NOWEARMAN
「MAN NOWEAR」
←INTERVIEW TOP
←MAGAZINE TOP
[MENU]
┣NEWS
┣DISC
┣ARTIST
┣MAGAZINE
┣MAILING LIST
┣CONTACT
┗HOME
Copyright(C) Spectrum Management Co.,Ltd. All rights reserved.